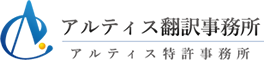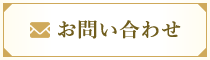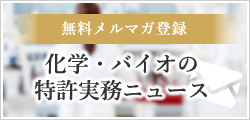ルート中之島ビル504
- ホーム
- 化学・バイオの特許「あるある」ブログ
- [017] サントリー ストロングゼロ 特許請求の範囲を比較 「wherein」
[017] サントリー ストロングゼロ 特許請求の範囲を比較 「wherein」
前回の続きです。
(日本語の特許明細書)
特許第4892348号
発明の名称:「アルコール浸漬物またはそれを用いた食品もしくは飲料およびその製造方法」
(英語の特許明細書)ヨーロッパの特許です
EP1792974 B
Title of the Invention:「Alcohol-dipped material, food or drink using the same and method of producing the same」
前回は、発明の名称を比較しましたが、今回は、特許請求の範囲(クレームと呼ぶこともある)を比較してみます。
【請求項1】
(a)原料果実および/または野菜の一種以上を凍結し;
(b)凍結物を平均粒径が1μm〜100μmとなるよう微粉砕し;
(c)微粉砕物をそのまままたは解凍してペースト状にしてから、15%〜100%のアルコールに浸漬して浸漬液を得て;そして
(d)浸漬液を添加する
工程を含む、食品または飲料の製造方法。
A method of producing a food or drink, wherein the method comprises the following steps:
(a) freezing one or more fruit(s) and/or vegetable(s) employed as a raw material to provide frozen matter;
(b) microgrinding the frozen matter until an average grain size of the frozen matter is 1 µm to 200 µm to provide microground matter; and
(c) dipping the microground matter in an alcohol having a concentration at which one or more components of the raw material can be extracted to provide an alcohol-dipped material, wherein the microground matter is dipped in the alcohol as it is, or the microground matter is thawed to give a paste which is then dipped; wherein the alcohol having a concentration at which one or more components of the raw material can be extracted is a 15% to 100% alcohol;
(d) providing a food or drink from the alcohol-dipped material.