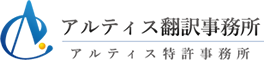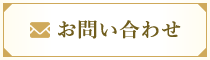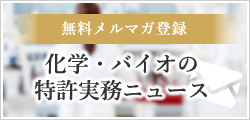ルート中之島ビル504
- ホーム
- 化学・バイオの特許「あるある」ブログ
化学・バイオの特許「あるある」ブログ
[033] 「人の流れが止まる」という初めての経験
2020/06/16[032] 令和2年 弁理士試験の日程が決まりました。
2020/06/03短答式筆記試験: 令和2年9月20日(日曜日)
論文式筆記試験(必須科目): 追って公表(令和2年11月上中旬を予定)
論文式筆記試験(選択科目): 追って公表(令和2年11月下旬〜12月上旬を予定)
口述試験: 追って公表(令和3年2月中旬〜3月上旬を予定)[031] 6月より通常営業に戻りました。
2020/06/01[030] 弁理士試験も延期になりました。
2020/04/14現時点では、9月以降の実施を予定しております。
[029] 時代はオンライン講義へと。
2020/04/06[028] 弁理士試験あるある談義
2020/04/03- 試験時間が足りない
- できるだけ速く書きたい
- (学習でたくさんの論文を書くので)できるだけ手が疲れないペンを使いたい
[027] カテキン類のはなし
2020/03/09
<参考特許>ヘルシア特許
特許番号 3329799号
特許権者 花王株式会社
発明の名称 「容器詰飲料」従来技術の記載から
カテキン類とは?
[026] カテキン類を含有するお茶の特許
2020/03/08発明のポイント
- 製法ではなく、「飲料」の特許である
- 特許請求の範囲に、パラメータが記載されている(「パラメータ特許」などと言われることもある)
- ヘルシアの基本特許
商品紹介ページ
技術分野
本発明はカテキン類を高濃度に含有する容器詰飲料に関する。
[025] 「おーいお茶 ナチュラルクリア製法2010」特許請求の範囲(3)
2020/03/07英語明細書と日本語明細書の比較
<日本語明細書>
特許番号4015631号
発明の名称「容器詰緑茶飲料の製造方法」
日本語明細書の特許請求の範囲は、以下のとおりでした。
【請求項1】
① 緑茶葉を70〜100℃の加温水にて抽出する抽出工程、② 得られた茶抽出液にシリカを添加して茶抽出液中のオリ成分を当該シリカに吸着させる吸着工程、
③ 酸処理された珪藻土を用いて珪藻土濾過を行う珪藻土濾過工程、
④ 殺菌工程及び
⑤ 容器充填工程
を含む容器詰緑茶飲料の製造方法であって、
②’ 吸着工程では、シリカを添加する茶抽出液を20〜40℃に冷却することを特徴とする容器詰緑茶飲料の製造方法。
これに対し、US7682643のクレーム1は、次のとおりです。
1. A method for manufacturing containered green tea beverage
having catechin content, wherein said method comprises:
① an extraction step wherein green tea leaves are extracted in hot water at 70-100° C., said extraction step resulting in a green tea extract;
② an adsorption step wherein after adding silica to the tea extract, said tea extract is brought into contact with silica while being cooled so as to reach 20-40° C. to absorb formulation components of a secondary sediment present in the green tea extract to said silica;
○ a silica elimination step wherein the silica is eliminated from the green tea extract;
④ a sterilization step; and
⑤ a container filling step.
「オリ」に関する表現
「オリ」=sediment
「二次的なオリ」=secondary sediment
飲料製造後の保存中に経時的に発生する「二次的なオリ」“secondary sediment,” which occurs gradually with time after manufacturing the beverage, during storage.
[024] 「おーいお茶 ナチュラルクリア製法2010」特許請求の範囲(2)
2020/03/06【0006】しかし、オリの原因物質を除去することにより二次的なオリの防止を図る方法は、緑茶飲料中に含まれる混濁・沈殿の原因物質を最終的に全て排除するものであったため、茶の香味に影響しオリの形成に寄与しない成分も多量に除去することになり、茶が本来備えている香味が弱くなるという課題を抱えていた。