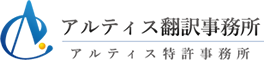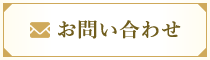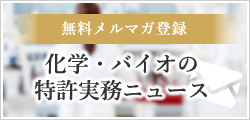大阪市中央区東高麗橋2-1
ルート中之島ビル504
ルート中之島ビル504
- ホーム
- 化学・バイオの特許「あるある」ブログ
- [009] よく知らない分野の本を選ぶ基準(私的基準ですが)
[009] よく知らない分野の本を選ぶ基準(私的基準ですが)
東京マラソンの一般参加中止が発表されてから、他の大会も次々と中止になっています。
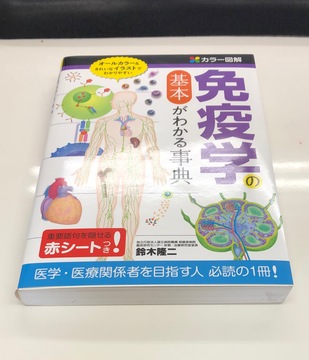
この前、熊本マラソンを走ってきたところですが、次に大会に出るのは暖かくなってからになりそうですね。
そんなわけで、ちょっと暇になってしまったので、自分なりの対策を。
とはいえ、マスクも売っていないし、とにかく自分の免疫力を高めて乗り切るしかないかなと。
不要不急の外出を避けること、とのことですので、事務所にこもって仕事をすることに。
事務所の本棚を見ると、ある本がふと気になりまして。
ちょっと読んでみようかと。
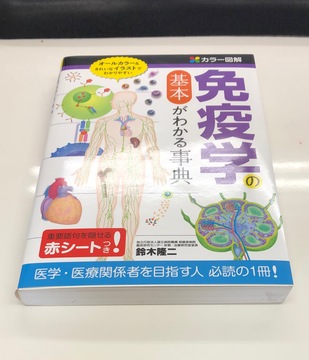
なんでこんな本が手元にあるかと言いますと。
元研究者とはいえ、特許翻訳の仕事で扱う仕事の中には、勉強したことがない分野も多々含まれます。
大学が工学部なので、工学系の本は一度は見たことがあるものが大多数なのですが、医学系になるとなかなかわからないことが多いです。
それでも、だんだん分野間の境界にあたるような技術も増えてきているので、本を読みつつ知識をアップデートしております。
というわけで、事務所には積ん読している本(読んでないんかい)がたくさんありまして。
化学・バイオの本(医学・薬学系も含む)で、よく知らなくて新しく勉強してみようと考えたときに、自分なりに選ぶ基準を作っています。
基準1 写真や図がたくさん書いてあること
単純に、文章だけで書いてあるよりもわかりやすいからです。上の本も「カラー図解」となっていて、身体のイラストなどが数多く用いられています
基準2 一般向けではなく、専門の人が読む本の入門書であること
普通に知識を得るだけなら、一般向けの本の方がわかりやすいのですが、目的が「特許翻訳に必要な知識を得ること」なので、はじめから専門の人向けの入門書(学習者向けなどもOK)を選ぶようにしています。
上の免疫学の本は、「医療・医療関係者を目指す人 必読の1冊」となっています。
基準3 実験のやり方が具体的に書いてあるような本
実施例、実験例などを訳すときに、どのような手順なのか文章だけではわからないことがあります。
そのときに、実験の手引き書のようなものがあると便利です。
でも、積ん読しとくだけではだめです(当たり前)。
ちょっと読んでみようかと思いまーす。